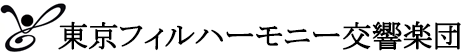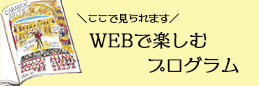インフォメーション

集中連載 ヘンツェのまなざし【第3回】
10月定期演奏会で取り上げる作品を通じ、 第二次世界大戦後のドイツを生き抜いた 偉大なる作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェの“視点”に迫る3回シリーズ。
最終回は、本公演を指揮するマエストロ沼尻竜典へのインタビューをお届けしたい。
8月、オペラの稽古場を訪ね、マエストロが見据えるヘンツェ像について伺った。
感覚的にわかりやすいその音楽はいわば「極めて整然とした激流」
取材・文:高橋 彩子 撮影:堀田 力丸
膨大な音数のすべてが“必要な音”。音楽の仕組みを知り尽くした凄み。

沼尻竜典のヘンツェ作品との出会いは、ベルリン芸術大学時代にさかのぼる。
「ちょうど留学しているとき、ヘンツェの『午後の曳航(裏切られた海)』が初演されたんです。三島由紀夫の原作を一生懸命読んでから聴きに行きましたが、原作も音楽も難しいなあと感じましたね。ヘンツェは当時からドイツ音楽界の権威。死んでから有名になるケースと違って、ヘンツェは若くして名声を確立しました。そういう立場になると、新作が少なくなる人も多い中、彼は書き続け、皆、今度はどんなものを書いたんだろうと、毎回楽しみにしていたわけです」
86歳で没するまでの60年以上、作曲活動を旺盛にこなし、話題作を発表し続けたヘンツェ。その楽曲の魅力は、どんなところにあるのだろうか?
「普段、現代音楽に馴染みがない人が聴いても、感覚的にわかりやすいところがあるのではないでしょうか。というのは、音はすごく多いけれど、その全てが、必然性をもって書かれているんです。現代の作曲家で、例えば先日来日したハリソン・バートウィスルなどは、豪雨の後の川じゃないですが、自転車とか靴とか木材とか、あらゆるものを飲み込んでどわーっと流れる、濁流のような迫力がある。一方、ヘンツェでは、同じ激流でも、流れているものが極めて整然としている印象です。まるで、豆腐工場や豆乳工場のレーンを大量かつ急速に流れる大豆が、一粒一粒きれいに揃っているような。従って、食べられないものを無理矢理食べさせられているような感じはしないんです」
こうしたヘンツェの音楽の特長は、彼が音楽史に連なる正統的な作曲家であることに依るという。
「ヘンツェは音楽の仕組みを知り尽くしていました。バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス……と続くアカデミックな流れの中に、彼もいた。アカデミックというと、日本ではネガティブなイメージを抱かれがちですが、やはり作曲とは、きちんとした理論に基づいてなされるものです。モーツァルトなんて、伝記作家の手にかかると、こっくりさんよろしく、神の啓示を受けて手が勝手に動いた、みたいな話になりがちだけれども(笑)、実際には幼少時から和声学や対位法を学び、ある程度、理論に沿って曲を書いた。現代の作曲家の中には、コンピューターを使ったりして、音をなんとなく置いた結果、実際にはその楽器で演奏できないようなものを出してしまう人もいますが、ヘンツェは、各楽器の性能と限界を熟知した上で、音を並べています。もちろん声にも詳しい。だから、精神論ではなく、理屈も全部わかって書いている凄みみたいなものがあるんですね」
上演に向けてスコアを咀嚼する際、直面するのは、ヘンツェならではの難しさ・おもしろさ。
「これは何だろう? という打楽器が、いろいろと入っています。その他の打楽器も多いのでバランスを取るのが大変です。あのスコアを全部、完璧に弾きこなすのは至難の技だけれども、もしかしたら、1年間、ひたすら練習し続けたら、完璧にできるかもしれない。そういう微妙な境目に難易度が設定されています。だからこそ、こちらはきちんと勉強し、奏者はしっかり弾かないといけない。そうすれば、音もよく鳴るようにできているのです」
共闘してきた東京フィルと共に、作曲家の初期作と代表作に挑む。

今回は、ヘンツェが20代で作曲した「ピアノ協奏曲第1番」と、70歳を過ぎて作った「交響曲第9番」の両方が演奏される。観客は、一人の作曲家のキャリアの初期と後期の作品を併せて楽しむことができるわけだ。
「50年近い間に、作曲家の語彙も表現の引き出しも増える。演奏家もそうだけれど、年を取ったほうが無駄がなくなりますね。夭逝したモーツァルトやシューベルトは例外として、大抵の場合、どの作曲家も若い頃の作品では力が入り過ぎる傾向にあります。指揮者で言えば、常に棒をブンブン振り回している状態。良い経験を積みながら年齢を重ねていけば、そこまでしなくても表現できることが多くなります」
もちろん、初期には初期の、円熟期には円熟期の魅力がある。
「遍歴と冒険は先へ進まなければならない。休息はない。未知の領域への第一歩は必ずしも技術的原則にのっとらなくてもよいし、ぜひとも《前方》を志向しなければならないというものでもない。(《前方》がどこにあるかなど誰が言いあてられるだろう)」(塚谷晃弘訳)
「『ピアノ協奏曲第1番』には、未来のヘンツェの芽がそこここに見受けられます。この曲に限らず、器楽作品でも交響曲でも、彼はよくピアノを使うのですが、これが実に難しい。端的に音が多いし、跳躍も多い。かといって、めちゃくちゃ弾きにくいわけではないんです。手の動きもフィジカルにきちんとしていて、音楽的だと思いますね。『交響曲第9番』の頃には、より聴かせ上手になっています。と同時に、表現上のチャレンジ精神もある。交響曲をたくさん書くうちにルーティンになってしまう作曲家もいますが、やはり優れた作曲家は、死ぬまで成長するんだなと思います」
ナチス時代を描いた小説『第七の十字架』に想を得て作られた第9番は、「脱走」から「救済」までの7楽章からなる。情景が目に浮かぶような、非常に雄弁な音楽だ。
「ヘンツェはオペラ作曲の大家。彼の第9番にはテキストもありますから、オペラ的手法も駆使しています。例えばモーツァルトが、レガートなメロディに細かい音符の伴奏を入れ、表面は平静なのに本当の気持ちはそうではないことを表したり、あるいはヴェルディが、『万歳!』とやっているところにヴィオラの低音のトレモロを入れることで不幸な結末を暗示したりといったことを、していますよね。そうしたオペラで使う表現法を、ヘンツェは自然にこの作品にも取り入れているんです。合唱を2群に分けて“木”と“人間”として対話をさせたり、オスティナートの間隔を少しずつ狭めることで緊迫感を表現したり……。緻密に作られています」
同じくオペラの作曲も手がける立場として、沼尻は、ヘンツェの作曲に対し、どのような印象を抱いているのだろうか。
「僕が今書いている初めてのオペラ作品は、ソングとか子ども向けオペラのようなものなので、全然彼の作品とは別物です。ただ、作曲出身の指揮者は、演奏者側から来た人とはだいぶ違うと言われます。どういうことかと言うと、“メロディが美しい”というところから入らない、必要以上に作曲家をあがめ奉らない(笑)。作曲家が苦労してこことここをつなげようとして、半音ズレちゃったから、無理矢理転調しているんだなとか、そういう、作曲家が触れられたくない部分も見えますから。逆にヘンツェのような『巧い』作曲家に対しては、格の違いも忘れて『巧すぎて悔しい』とも思うし(笑)」
そうした多彩な音楽世界を、東京フィルと共にどう作り上げるのか? 期待は高まる。
「東京フィルとは、彼らの半分の前身である新星日響も含め、現代作品や、それまで日本初演されていなかったオペラなどを、たくさんやってきました。昔のプログラムを見ると、よくまあこんなにというくらい(笑)。だから、東京フィルと僕とは根っこが同じ。チャレンジングなことが大好きなのです。最近は、オペラをご一緒することが多い中、今回のような企画をやるのはお互いに新鮮です。オペラ作家としても交響曲作家としても活躍したヘンツェに、オペラが得意な東京フィルと共に取り組むというのは、とても楽しみですね」
(インタビュア・プロフィール)
たかはし・あやこ/ライター・編集者。古典芸能から現代劇、舞踊、オペラまで舞台芸術全般にわたって取材・執筆。近年は、文楽とその置かれた状況に関する執筆やラジオ出演も。音楽は客席で楽しむほか、アマチュアオーケストラに第2ヴァイオリンで参加。ブログ:http://blog.goo.ne.jp/pluiedete