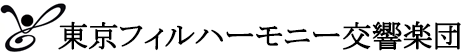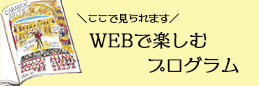インフォメーション

集中連載 ヘンツェのまなざし【第2回】
10月定期演奏会で取り上げる作品を通じ、 第二次世界大戦後のドイツを生き抜いた 偉大なる作曲家ハンス・ヴェルナー・ヘンツェの“視点”に迫る3回シリーズ。
第2回となる今回は、「ヘンツェ」と「ピアノ の関係を探る。
さらなる独自性を拓いた「ピアノ協奏曲」
文:小沼 純一
バレエ・ダンサーとしての「ピアノ」

ピアノ協奏曲第1番完成の前年(1949年)、
ハンス・ホフマン教授と22歳のヘンツェ。
cSchott Promotion / Ursula Helbich
ハンス・ヴェルナー・ヘンツェの音楽を聴くたのしみのひとつは、わたしにとって、躍動感です。言い方を変えれば、リズム、あるいは、時とともにあるうねり、でしょうか。
たしかに音のならびは、長調や短調、あるいは中世の教会旋法や非西洋圏の音階といったものではありません。その意味ではとっつきにくいかもしれない。でも、「ピアノ協奏曲 第1番」の冒頭を聴いてみてください。弦楽器がすべてオクターヴでメロディを弾いている。併行してピアノが分厚い和音を叩いてゆく。ここでおきているゆったりとしたうねりに、上半身をそわせ、うごかしてみたら、どうでしょう。あるいは、第3楽章、3拍子のリズムがはやいテンポでぐんぐん進んでゆくのを、足先でとってゆく、とか。アタマにはいってくる以上に、からだから、音楽がはいってくるのではないでしょうか。
この「ピアノ協奏曲 第1番」、スコアをながめて気づいたことがいくつかありました。
3つの楽章は急―緩―急の古典的なたたずまいをもっているのですが、それぞれには「アントレ(Entree)」「パ・ド・ドゥ(Pas de Deux)」「コーダ(Coda)」とついているのです。これ、言うまでもなく、バレエに由来しているわけです。いわゆる「協奏曲/コンチェルト」、18世紀以前の宮廷でのスタイルとは異なって、19世紀ロマン主義の時代には、ソリストがオーケストラをむこうにまわし、派手なテクニックを披露する、というような音楽でした。ソリストとオーケストラは対立しながら、より高次のところに至るのが目指されていました。いわば弁証法的なつくりだったのです。でも、ヘンツェはここでわざとバレエの用語を用いることで、協奏曲というタイトルをつかいながらも、対立を無化してしまいます。「パ・ド・ドゥ」は、直訳すれば「2人のステップ」、男女2人の踊り手が一緒に踊ります。タイトルとして「パ・ド・ドゥ」が第2楽章に与えられていますけれども、「アントレ(入場)」と「コーダ(締め)」とあわせて全体がピアノとオーケストラによる「パ・ド・ドゥ」ととらえられます。
そんなふうにみてみると、ピアノははじめからオーケストラと「ともに」ありながら、ちょっと違った動きをしていることに気がつきます。ひとりで目立ったり、先導したりするのではなく、オーケストラの一員のように振る舞ってさえいます。ピアノの右手と左手の動きや音型に注目してもおもしろい。とてもこまかい音型を弾きまくるというよりは、おなじ音、和音の反復が多かったり、オーケストラとはずれたところでリズムを弾いていたりします。モーツァルトのピアノ協奏曲は、オペラにおけるアリアを、歌手のかわりにピアノが演じている、とみなすことができますが、この協奏曲ではバレエ・ダンサーとしてピアノがあるととらえてみたらどうでしょう。
「ピアノ協奏曲 第1番」を作曲した1950年、ヘンツェは、フランクフルトから1時間足らずのヴィースバーデン、そこのヘッセン国立劇場バレエ団の指揮者兼音楽監督に就任しています。バレエやダンスの音楽が、コンサートで演奏されるべき音楽とともにあるのは偶然ではなさそうです。
「遍歴と冒険に休息はない」
年譜をひらいて、ヘンツェの1940-50年代をみてみると、ほぼ最初に掲げられているのはピアノ、フルート、弦楽のための「室内協奏曲」、1946年の作品です。作曲家は1926年の生まれですからこのとき20歳。編成の小ささもあるのでしょう、こぢんまりしたバロックの協奏曲のような感触、初々しさや可愛らしさがありますし、一方、翌年のピアノと弦楽、金管、打楽器のための「コンチェルティーノ」も、ピアノの書法は異なっていますけれども、両者は親近性のある作品になっています。
それが、おなじように、ピアノとオーケストラという編成でありながらも、「ピアノ協奏曲 第1番」では大きく変わるのです。オーケストラの編成も大きい。ダイナミックです。ある作曲家=指揮者のことばを借りれば「ブレイクスルー」となった作品でさえあるのです。とはいえ、先に記したように、ロマン主義的な肩肘張った協奏曲ではない。その仰々しさを回避するために作曲家がとったのが、バレエの「パ・ド・ドゥ」のかたちだったのです。そしてまたここには、先人であるストラヴィンスキーやバルトーク、あるいはシェーンベルクを想起させる先人のピアノの書法を随所にみることができます。
この作品から、ヘンツェはより独自の音楽へとはっきりと進んでゆくことになります。作曲家はまだ24歳。同世代の「前衛」の作曲家たち、たとえばルイジ・ノーノ、ピエール・ブーレーズ、カールハインツ・シュトックハウゼンは、みな、まだ大きな作品を発表していない時期です。
「遍歴と冒険は先へ進まなければならない。休息はない。未知の領域への第一歩は必ずしも技術的原則にのっとらなくてもよいし、ぜひとも《前方》を志向しなければならないというものでもない。(《前方》がどこにあるかなど誰が言いあてられるだろう)」(塚谷晃弘訳)
ヘンツェが1950年代に書いた文章から引きました。こんなところに、いま私たちがいる21世紀、そして文章が書かれて半世紀、作曲家自身が没して1年という時期に読みかえしてみると、考えさせられるものがあります。当時、1950年代、ヨーロッパでおこっていた前衛的な動向、何人かの作曲家たちとその亜流の音楽を想いおこしてみるわけです。
この先、ヘンツェは「ピアノ協奏曲 第2番」を1967年に、1973年に「トリスタン」と名づけられた、ピアノとテープ、オーケストラのための作品を発表することになります。これらが規模の点でもひびきの点でもどれほど異なった作品であるか、それでいてヘンツェのもっている躍動感が生きていることについては、ぜひ、機会があったら接していただけたらとおもいます。
(プロフィール)
こぬま・じゅんいち/音楽・文芸批評。音楽文化論。早稲田大学教授。著書に『魅せられた身体』『武満徹 音・ことば・イメージ』『映画に耳を』ほか。編著に『武満徹エッセイ選』『高橋悠治対談選』『ジョン・ケージ著作選』ほか。第8回出光音楽賞(学術・研究部門)受賞。