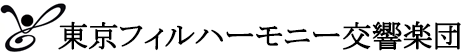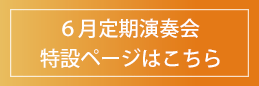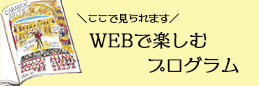インフォメーション
2014年3月9日(日)

日本における近代西洋音楽は1880年代にまで遡る長い歴史を持ち、その頃からさまざまなジャンルで盛んになっていきました。1860年代から1870年代にかけての日本は激動の時代で、その過程で文化的な亀裂が生じ、音楽の世界も揺れ動きました。幕府の崩壊と、新たに始まった20世紀へと続く明治天皇の長い治世下で進められた西洋化政策は、産業革命の恩恵をこの国にもたらしただけでなく、文化的な変化の大波も起こし、驚くほど劇的に世の中を変えました。着物と日本刀は廃れ、フロックコートと顎ひげが流行りました。音楽も、方向転換を余儀なくされました。日本独自の1,300年にもおよぶ素晴らしい和楽器の伝統は学校教育から締め出され、その代わりに西洋音楽で使われるまるで機械のような楽器、つまりピアノ、多くのキーをもつ管楽器、パイプオルガン、「ハイテク」ともいえるオーケストラ楽器が導入されました。その結果、今日まで1世紀以上におよび、日本の義務教育における音楽教育は西洋楽器をもちいた音楽ばかりでした。今日、日本には各都市に多くの熱心なクラシック音楽ファンがおり、東京だけで主要なプロ交響楽団が6団体あります。テレビでは毎日クラシック音楽ファン向けの番組が放送され、書店にはクラシック音楽関連のさまざまな雑誌・書籍が並び、そしてご存知のように、日本は世界の舞台で引けを取らないクラシック音楽の演奏家と指揮者を多数輩出してきました。
 |
現存する日本最古の交響楽団である東京フィルハーモニー交響楽団は、シンフォニーからバレエ、オペラにいたるまで、幅広いクラシックのジャンルで、常に先頭を走り続けてきたオーケストラの一つです。今では、年間を通じてシンフォニーとオペラ両方の定期演奏会を行っている日本で唯一のオーケストラとなっています。ゆえにニューヨーク市民にとって、創立100周年記念ワールド・ツアーで、大植英次の卓越した指揮のもと、このダイナミックなオーケストラをヨーロッパとアジアに先がけて当地に迎えられることは、誠に光栄です。実は、同楽団は3年前にニューヨークを訪れるはずでした。1911年創立の東京フィルは、2011年に100周年を祝ってワールド・ツアーの催行を計画していましたが、その年、東北地方沿岸部を大地震と津波が襲い、祝賀コンサートの開催は不可能となりました。
しかし、2011年の震災から3年という時間は、東京フィルにとって予定されていた曲目をもう一度検討する機会となったようです。当初、同楽団は海外の聴衆に馴染みのあるクラシックの曲目を、東京フィルならではの定評ある演奏で共に祝うことを予定していました。しかし、この3年の間に深く掘り下げた探求が行われたように思えます。問いはもはや、「自分たちが演奏したいと思えて、聴衆にも喜んでもらえるクラシック音楽とは」というものではなく、「音楽が人類にとって意味するものとは」、「いかに音楽は苦難に見舞われたとき、人々の間に絆をもたらし、心を一つにするのか」、「音楽とは、人間が心の奥底で感じる必要性や最も身近な感情を表すきわめて大切な表現方法の一つではないだろうか……一体全体、そうした音楽とは何だろう?」ということを問い直す方向に変化していったのではないでしょうか。不安定な状況にあるとき、人は自らのルーツやコミュニティと向き合うことで、癒しを感じるように思われます。たとえば、チャイコフスキーは長年にわたるロシアの苦悩と自己探求の中で歴史へと向かい、そのなかで深い基層となっているロシア民族音楽へと向かいました。そのために、彼の音楽は最初フランスで「ありきたりだ」、「洗練されていない」などと酷評を受けました。しかし、チャイコフスキーは、自身のロシアの音風景を慈しんだことで欲求と感情の扉を開くことに成功し、その音楽は、当初異なる音楽文化に慣れていたために抵抗感のあった私たちの耳にも親しみを感じさせるものとなり、今では渇望をすら覚えさせています。ストラヴィンスキーも、多彩な文化的な音風景を有していましたが、自身と共鳴する音へと沈潜していきました。2人とも、民族舞踊にも深く関わるようになったのです。
東京フィルは、再検討の結果、ワールド・ツアーの曲目に、2人の20世紀の日本人作曲家の作品を追加することを決定しました。彼らの曲は大胆かつ難しい曲ですが、チャイコフスキーや他の多くの作曲家のようにそれぞれの理由で、自らの文化の深層から昇ってくる音楽に回帰した末に作られたものです。黛敏郎(1929-1997)は、日本の(そして世界の)最古の管弦楽として1,300年の歴史を持ち、舞楽の踊り手たちに伴っていた雅楽へと回帰し、片や小山清茂(1914-2009)は、自然に生まれてきた民謡や祭囃子などを取り入れました。
メシアン、メノッティ、武満、シュトックハウゼン、ケージ、バーンスタインと同時代の作曲家である黛は、東京藝術大学を卒業後パリで学び、日本に帰国してから前衛作曲家、またダイナミックな指揮者として、輝かしいキャリアを歩み始めました。今回東京フィルは、黛自身が指揮することを好んでいた管弦楽曲である、壮大なバレエ音楽「BUGAKU」を曲目に選びました。
 |
私は「BUGAKU」の悲運には、2つの要素があると思います。まず、この作品がニューヨーク・シティ・バレエ団の振り付けのためにバランシンによって委嘱されたということ自体は幸先のよいことでした。1959年にニューヨークで宮内庁式部職楽部が雅楽・舞楽を演奏したのを鑑賞したバランシンは、雅楽のように物語性を排した純粋な作品を作曲して欲しい、と黛に依頼したのです。ところが、こうして生まれたバレエ「BUGAKU」(1963)は、バランシンの作品の中でも特に不評だったものの一つとなってしまいました。1963年の初演では「聴衆がクスクスと笑う声が聴こえ」、バランシンが付け加えたエセ日本趣味のダンサーの様式は、何人かのニューヨークの批評家によれば「気恥ずかしさを覚えさせる」ものでした。舞台には神聖な場所として境界を仕切るために、伝統的な舞楽と同じく緑色の敷物が敷かれ、赤漆を塗った柵が設けられました。舞楽では通常、この舞台で、雅楽の演奏に合わせて男性の舞人が、象徴的に存在する神々に感謝を捧げるために崇敬の念を表す舞を奉納します。黛は、神への捧げ物として制約された舞楽という音楽の領域を広げて西洋の管弦楽曲と見事に組み合わせ、双方の不協和音を独創的に生かしつつ、伝統的な音色と拍子を反映させた現代的音楽を再創造しています。しかし、バランシンが男性の舞人をチュチュとトゥシューズを身に着けた若い女性ダンサーに置き換え、あからさまに官能的なデュオの振り付けを施したことで、舞楽と舞の関係性は崩れ去りました。
雅楽の非現実的な神霊の世界とかかわる音楽体系を構成する旋律、音色、テンポ、拍子、音階に馴染みがないとしたら必然的に、西洋の管弦楽の楽譜の中に黛が巧みに組み込んだ雅楽の「引用」を聴き取ることはできないでしょう。これが2つ目の問題でした。今夜、私たちには、聴衆として、2度目の挑戦に臨む機会が残されていると考えます。今晩の演奏には視覚的要素は伴いません。オーケストラが奏でる宇宙を思わせる調べに身を任せて、自由に想像の翼を広げることができることを願っています。
小山清茂の「管弦楽のための木挽歌」は元々劇中音楽として作られたもので、好評を博したためさまざまなラジオの音楽劇で主題として使われ、最終的に完全な管弦楽版として改訂されました。この曲は、勤勉さ、粘り強さ、忍耐、コミュニティとのつながり、祭りで溢れ出す生の喜び、陶酔、しかし下品でない性質など、日本人が日本人らしさの真髄として捉え、慈しんでいることを反映させた主題を含んでいます。その音楽は、故郷の景色と日本の音風景への愛情を感じさせます。
曲は、山奥の森にいる木挽き職人が一定の拍子で重い鋸を挽く音で始まります。この音は、駒の近くで弓を弾く弦楽器の音で表現され、12音音階のあらゆる音を駆使して奏でられます。そして、木挽き職人が静かに口ずさむ即興の歌が聴こえます。歌は人から人へとだんだん伝わっていき、やがて村の神社の夏祭りの音楽に変わっていきます。集まった若者たちの声を象徴するのは、ピッコロの音色です。他の管楽器が木挽き職人の歌の旋律を取り上げ、変奏が繰り広げられます。オーケストラ全体が演奏に加わって祭りはさらに盛り上がり、手拍子と繰り返される掛け声のユニゾンで最高潮を迎えます。そしてある日木挽き職人の歌は町にも伝わり、出前の少年たちが口ずさむ歌が町に響きます。町全体に伝わっていくにつれて、さらに多くの楽器が加わっていきます。終極に向かって膨張していく西洋音楽とは対照的に、この作品は元の村に戻り、木挽き職人の歌を静かに、瞑想的に奏でるバス・クラリネットの旋律で終わります。癒される食べ物があるように、癒される音楽もあります。小山は彼自身の癒しの音楽を探求したのでした。民謡がどのように生まれたのかを語るのが、小山の作ったこの曲の主題と思われます。まず働き手が、自らの手で行っている労働のリズムに合わせて歌を作り、それが村の中で伝わり、やがて村から町へと広がっていくことで伝統となり、私たち全員のものとなります。そして、この音楽の持つ精神が、私たちに勇気と強さを与えてくれるのです。
クラシック音楽はヨーロッパの中心から1、2世紀をかけて国際的に広がっていき、今や世界各地で愛され楽しまれています。こうした大きな広がりを見せたのは、新しいテクノロジーがすべての人にクラシック音楽に直接に接する機会をもたらしたことによるものでもあることは、間違いないでしょう。耳慣れない音楽が突然響き始めたと思ったら、いつの間にか昔から聞き慣れた音楽のようになります。馴染みがより深くなることで、相互に創造性を開花させ、大きな喜びを与えます。同時に、さまざまな国民的多様性やオーケストラの個性が世界中で画一的なスタイルへと収縮していく危険があるとの悲嘆も聞かれます。そのような事態が起こらないことを願いましょう。人間にとってのもう一つの大切な言語である「音楽」を、たとえ文法や発音などに不慣れでも理解できた瞬間は、刺激的であるとともに心地よい体験です。東京フィルハーモニー交響楽団には、記念公演の機会を待たずに、彼らが血肉化しているバッハやベートーヴェンだけでなく、日本人作曲家によるクラシック音楽の数多くの曲目からの公演を、毎年催行していただきたいと願います。彼らは、私たち西欧の聴衆に20世紀の西洋のクラシック音楽についても多くのことを教えてくれ、21世紀の音楽の世界についても語るべきたくさんのことを有しているのですから。
 |
著者プロフィール
バーバラ・ルーシュ/Barbara Ruch
コロンビア大学東アジア言語文化学部名誉教授、中世日本研究所:日本文化遺産イニシアチブの創設者兼所長。また、コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センターの創設者・初代所長でもある。さまざまな方面の日本研究における多くの先駆的研究により数々の受賞歴を持ち、1999年には日本政府より勲三等宝冠章を授与された。2005年より、日本および世界規模で和音楽の復興を支援する活動を続けており、米国の大学における雅楽管絃アンサンブルの設立に貢献した。